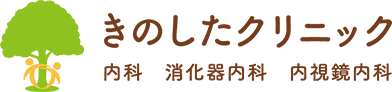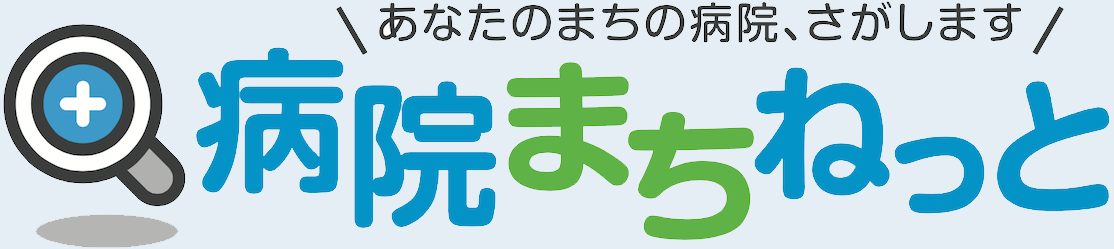慢性胃炎の原因の多くは従来からヘリコバクター・ピロリ菌の感染によるものが多く、主に幼少期に成立した感染によりピロリ菌が胃の中にすみついて胃粘膜に萎縮性変化を引き起こし、胃・十二指腸の潰瘍が生じたり、長期にわたる慢性胃炎から胃がんを発生するリスクが高まります。
近年ではピロリ菌の適切な除菌治療の普及により、徐々に感染している方が減少してきています。ただし、胃痛などの症状や検診での異常指摘によりピロリ菌感染が判明する方はまだまだ多いです。
ところで、ピロリ菌感染がなくても萎縮性胃炎を生じる病気に自己免疫性胃炎(autoimmune-gastritis:AIG)という疾患があります。自己免疫性胃炎は胃底腺粘膜が体質(自己免疫機序)により引き起こされる慢性炎症で、抗胃壁細胞抗体や抗内因子抗体といった自己抗体(本来は細菌などの免疫に関与する抗体が、自分自身を攻撃してしまう)のため胃粘膜にある壁細胞という部分が破壊され消失することで胃粘膜の萎縮が起こり、胃酸の分泌が低下して低酸・無酸状態に陥ります。以前は稀な疾患と考えられていましたが、世界的には1~2%と推定されており、この病気の認識が高まるとともにこれまで想定されているよりは多い頻度で存在すると考えられています。日本においても診断されるケースが増えており男性よりも女性の頻度がやや高いとされています。
ピロリ菌感染に伴う萎縮性胃炎は胃の出口の方から徐々に萎縮が広がります。一方、自己免疫性胃炎は胃の出口の方の萎縮は軽度であるのに対し、胃の真ん中や入口の方で萎縮が強い(逆萎縮)傾向があり、注意して観察すると異なる内視鏡像を呈していることに気が付きます。
多くの場合無症状で長期にわたり萎縮性胃炎が進行していきます。進行すると胃酸分泌低下による鉄欠乏や、内因子低下によるビタミンB12欠乏の状態となり、貧血を認めることがあります。橋本病などの甲状腺疾患をはじめとする自己免疫性疾患の合併などをきっかけに見つかることもあります。しかし進行しても無症状のことが珍しくありません。そのため上部消化管内視鏡(胃カメラ)を行ってはじめて診断がつく場合が珍しくありません。また胃がんリスク層別化検診いわゆるABC検診でD群(血中Helicobacter pylori抗体陰性かつペプシノゲンI値とペプシノゲン I/ ペプシノゲンII比が低下した場合)ではピロリ菌による萎縮性胃炎が進行した結果ピロリ菌が自然排菌(除菌治療を行っていなくてもピロリ菌が自然に消失すること)が起こっていることもありますが、内視鏡所見が異なるため調べると自己免疫性胃炎の診断に至るケースが当院でもあります。
自己免疫性胃炎の場合にピロリ菌の感染診断や除菌判定に用いる尿素呼気試験が陽性(偽陽性)になることがあり、繰り返しHelicobacter pylori除菌を行われている場合があります(「泥沼除菌」という名称もあります)。除菌失敗の原因はピロリ菌が治療で使う抗生剤に対する薬剤耐性(効かなくなってしまっている)ことが多いですが、実は自己免疫性胃炎であったというケースもあります。
自己免疫性胃炎の確定診断は内視鏡検査のほかに病理診断、血液検査などを含め総合的になされます。病理診断には通常の染色法以外の方法を追加でより詳しく調べる場合があります。また血液検査は抗胃壁細胞抗体や抗内因子抗体を調べますが、現時点で保険診療では認められていないため、当院ではまず安価なほうの抗胃壁細胞抗体から調べるようにしています。
胃壁細胞の破壊により高ガストリン血症をきたしてくるため、胃癌や胃神経内分泌腫瘍の合併率が高くなってきます。実際以前に当時の勤務していた病院において早期胃がんに対して内視鏡治療(粘膜仮想剥離術:ESD)を行った方の多くはピロリ菌陽性者や既感染の方でしたが、ピロリ菌陰性の方を調べると自己免疫性胃炎であった方が多くおられました。
ただしピロリ菌感染による萎縮性胃炎は除菌治療という治療法があるのに対し、自己免疫性胃炎には現時点で有効な治療法はありません。
したがって早期胃がんの早期発見、早期治療を行うためにはピロリ菌除菌後の方と同様に1年に1度の定期的な上部内視鏡検査を行うことをお勧めしています。
またそもそも診断が確定しないと注意のしようがありません。疾患の認識をしていない医師では適切に診断できないと思われますので、このような疾患を十分認識された医師のもとでの検査を推奨します。